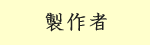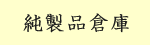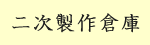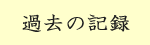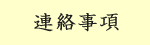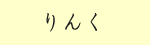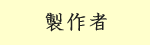
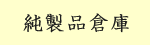
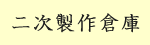
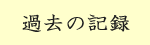
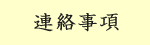
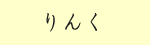
一話 二話 三話 四話 五話 六話 七話
片想い
第三話
それが、昼休みにあったささやかな出来事だった。春原は杏を見つめながら小さく息を吐き、目の前にやってきた杏を見つめ返す。ぽつぽつと降る雨をもたらしてる雨雲が日の光をさえぎっているためであろうか、彼女の表情はいつもの明るさを装いながらも、影の部分を隠せないでいるように思えた。そしてそれを気のせいだと片づけることが彼にはできそうにもなかった。
ややためらいがちに春原は口を開き、うまくいってるの? と、そう尋ねた。
「何をよ」
杏の言葉には力が込められていない。彼の問いかけを無視することも出来ず、跳ね除けることも出来ないように、彼女の瞳が春原を捉えていた。
「あいつとのことに決まってるだろ?」
あいつ、という代名詞が指し示す相手が誰なのか、というような逃げを杏は一切しなかった。ただ目の前にいる春原からわずかに視線をそらし、抑揚の抑えられた声で応じた。
「……あんたには関係ないじゃない」
「……ないこともない、って僕は思ってるんだけどね」
軽薄な口調で、けれど瞳にだけは想いを込めて、彼はそう呟くように言った。その視線を受ける杏もまた、勢いを失った鳥のような、力無い瞳を春原に向けている。
「僕は、杏の味方だからさ」
「……じゃあ、あの手紙は何よ? あれって、その……」
杏は困惑にも似た成分に幾ばくかの照れを混ぜ合わせた表情で、彼を見つめた。
「ラブレター、よね?」
ぽつぽつと雨が降る中、彼女は頬を微かに染めた。その姿は、どう控えめに見ても可愛らしかった。いつもの強気な杏ではなく、弱く脆い雰囲気を纏わせながら、時折顔の側面にリボンでまとめた髪に手を伸ばし、なでるように動かす。
「かも、しれないね」
そんな彼女を見つめながら、春原はそう言って笑って見せた。本心を言えば、彼はそんな彼女を見て、彼女に渡した手紙が無駄に終わらないのではないか、と思いたかった。あるいは、そう誤解したかった。けれど、そうはならないだろうということを、彼の最も奥底で冷笑的に自らを眺めやろうとするもう一人の自分は理解してしまっている。そしてそれが正しくないと決めつけることを、できそうにもなかった。それは突き詰めれば、自らに何らの魅力がない、と認めてしまっていることの証左であろう。だが、そのことを無意識に認められるようなことは、彼がサッカーから遠ざかざるをえない時期と同じくして、失われてしまっていた。
「かもしれないって……じゃあ、どういうつもり?」
杏の訝しげな問いかけに、春原はわずかに吐息を漏らして呟くように言った。
「今、身をひいたら……きっと後悔するよ?」
「なんのことよ」
彼の言葉に杏は即座に反応するように応じて見せたが、そこにはいつもの彼女らしい勢いのかけらさえ見いだすことができない。力の込められていない瞳はやや暗く春原を見つめてきていた。
「好きなんだろ、岡崎のこと」
「なっ……」
彼がごく当たり前のことを口にするように言ったその言葉に、杏は一瞬何も言えずに固まってしまったように、小さな声を漏らすだけで、驚いたように彼を見返してきている。
風が少しだけ強く吹く。雨がほんのひと時だけ勢いを強くし、コンクリートの屋上に小さな痕跡を残していった。
「……どうして」
ややあって、杏は誤魔化すことを諦めたように吐息を大きく漏らし、そして一度視線を春原からそらした。空には徐々に厚くなろうとする雨雲が、その上に広がる青空を覆い隠していた。外の世界は本来ならば秋の日差しを浴びて明るく見えているはずだったが、今はいつもよりも暗く感じられた。
「どうして、そう思ったの?」
「分かるよ。杏のことなんだからさ」
春原はそう言って、そして口を閉ざす。それ以上に理由の説明等必要ない、あるいは他に明確な理由などない、そう告げるように彼の視線は彼女に向けられていた。
「……」
そのままお互いに口を開かずに沈黙の帳が数瞬の間屋上を覆った。その沈黙を、杏が躊躇いがちに破る。心の奥底に眠らせておこうと決めていた、けれどそうしてしまうには余りに強い朋也への想いが、彼女の心の殻を打ち破ってしまったようだった。
「……そうね、確かにそうだわ。あたしは、あいつが……朋也のことが、さ」
恋を語るというには余りに苦く切ない表情を垣間見せながら、彼女はそう呟くように言って、吐息を漏らした。そこには恋に身を焦がす熱さは確かに含まれてはいたであろうが、それ以上にその熱さとは対極にある哀しさを春原に感じさせた。
「今日の昼休み、いつものようにやって来なかったのは……諦めたから?」
優しく問いかける春原の声質には憐憫の感情は一切含まれていなかった。もしその成分がかけらでも含まれていたならば、杏は即座にどこからともなく辞書を取り出し、彼にいつものように攻撃を加えていたであろう。そのような辞書による一方的な攻撃は日常の一幕にも似た情景として、彼女の記憶に残されている。
この場においてそうすることで、この屋上における会話を打ち切ることは容易だったが、彼女にはどういうわけか、それをなしえないだけの感情が心の奥底に存在していた。目の前の男子生徒がヘタレだと信じて疑ってこなかった彼女だったが、あるいはその評価は少なくともこの場所においては否定されるべきであるかもしれなかった。あるいは春原がそうではないと、心のどこかで思っていたからなのだろうか。その思考を完全に否定することができず、杏は小さく頷くしぐさを見せた。
「そうかも……しれないわね」
そう呟いた彼女は今にも泣き出しそうな、という表現が最もふさわしいと、春原には思えた。
思わず彼女を抱きしめたくなり、けれどまだそうすることはできないのだと、彼は知っていた。
そうしたところで、彼女は春原の想いを受け入れはしないだろう。彼がもたらすであろう温もりに身を委ねたりはしないであろう――そうしてほしいとは願うけれど。
それは彼女が、朋也に向けた想いを語った時に見せた表情が教えてくれたことだった。たとえ彼女にとって春原陽平という男が魅力にあふれた存在であったとしても、同時に二つの恋を併存させられるほど藤林杏という少女は小器用ではなかった。
そしてそうだからこそ、その強さともろさを併せ持った彼女だからこそ、彼は彼女に恋をしたのだ。そしてその恋が届かないと知った時から、せめて彼女が笑ってくれるようにと願い続けてきたのだから。
「……朋也ね」
彼女は視線を旧校舎の一角、演劇部室があるあたりへと向ける。ここからは直視することはできないが、大体の位置はあっているはずだった。
「あたしとたまたまふたりになった時でさえも、あたしの話題はしないのよ。いつも、りえか、すーちゃんのこと……昨日も、それに今日だって、そうだったし。だから、あたし」
淡いアメジストを思わせる瞳には涙が光っている――ように春原には思えた。何かを言うべきであった。けれど、彼自身が見るところでさえ、朋也の想いは――本人が気づいているかどうかは別として――少なくとも杏には向けられてはいないように思えてならなかった。
それでも、彼女をこのままにしておいていいはずがない。彼女には笑っていてほしかった。それが誰のそばであれ。
「もしかしたら、逆転ホームランの一発が期待できるかもしれないな、って思って」
彼女の哀しげな横顔を見つめながら彼はそう言った。この場においては不適当な例えであるかもしれなかった。サッカーを例えにした方が良かったかもしれない、と一瞬だけ悩み、けれどその思考自体に小さな苦笑を浮かべた。その名前が示すスポーツに、彼は愛憎半ばする想いを抱いていることを忘れることはついにできなかった。
この恋は、と彼は思う。
藤林杏という少女に向けられた彼の恋は、いずれ決着するだろう――あるいはすでに結末を迎えているのかもしれないが。何年かのち、彼がこの学生時代を思い出すときには彼女への想いはどのような色を散りばめさせて、彼の脳裏に浮かぶのだろうか。後悔だろうか。追慕だろうか。ずっと忘れることはできないのだろうか。それとも、その頃には思い出すこともないのだろうか。
そのいずれであったとしても、彼は後悔だけはしたくなかった。サッカーのときにように――それを比較対象とすることに彼自身いら立ちを覚えずにはいられなかったが――あの時こうしていれば、などという思考を抱き続けたくなかった。
彼にとって、杏への想いは単純な色彩だけを伴っていたわけではない。彼が抱いている想いが恋だと気付いた時には、すでに目の前の少女は彼ではない相手を想っていたのだから。彼女は何も言おうとはしなかったけれど、朋也ほどの鈍さを感性に含めさせてはいない彼には気づかざるを得ないことだった。
「……陽平?」
視線を彼へと巡らせ、彼女は見つめてくる。そこには幾許かの期待や希望と、そして多くの諦観や悲しみを同居させた少女の表情が浮かんでいる。彼女の視線を受けて、春原はわずかな吐息をもらした。それまでの思考を脳内から追い出し、彼にとっての悪友に恋する少女を見つめ返した。
「確か……はっきり覚えていないけどさ。何日後かは岡崎の誕生日なんだろ? だったら、そのときに何かプレゼントしてさ……」
そこで一度言葉を切り、春原は息を整えた。杏の想いが朋也へと向けられている以上、彼女の背中をはっきりと押したかった。けれどそれが同時に自らの想いが永遠に届かなくなるかもしれないということと同義であることに気づかない春原ではなかった。その覚悟はできているはずだったけれど、それでも躊躇ってしまう。けれど、何度目かの呼吸のあとで、言葉を続けた。彼がこんな場所で彼女を待っていた理由を思い出しながら。
「……告白したら、どうかな。あいつに、さ」
杏はその言葉に、すぐに返答しようとはしなかった。視線を彼から学校の前庭、長い長い坂道へと通じるその場所へと向ける。
「……ぁ」
そのとき、彼女の口から小さな声が漏れる。こらえきれない吐息が声を発せさせたような彼女の横顔は哀しげであり寂しげだった。大切な宝物を失くしたこどもほどの純粋さだけを内包しているわけではなくても、それでも思わず追いかけようとするように手を伸ばすそぶりをする彼女の想いの、少なくとも心の水面に浮き出た氷山の一角にも似たかけらを示しているように、春原には思えてならなかった。
彼女の視線の先には、朋也が校門に向かって歩いていた。そしてそのそばにはふたりの女子生徒が、寄り添うように歩いている。二人がいる場所からだと、彼やその少女たちの表情を見ることはできないけれど、朋也のそばにいる少女たちが、りえと杉坂だということを、春原は容易に理解できた。
もしかすれば、彼女にとって、彼の手紙は迷惑なものであったのだろうか、という思いがよぎる。彼が呼び出さなければ、杏もまた朋也たちの間に割り入ることができたのかもしれないのだから。
だが、春原がそのことを口にして謝罪しようとした時、杏の口がゆっくりと躊躇うように、開かれた。
「告白なんて……できるわけがないじゃない」
その言葉は余りに力なく、そして彼へと向けられた瞳には決意の色が垣間見える。そしてそれが、決して自らの望みをかなえようとする決意だとは思えず、春原は杏を見つめ返した。
朋也と、そしてりえや杉坂、杏の関係のすべてを、春原は知る由もない。けれど、目の前の彼女を見ていると、容易に想像が付きそうであった。
おそらく彼女は一歩――あるいは数歩――下がってしまおうというのであろう。双子の妹が朋也に恋をした時に身を引こうとした時のように。
きっと、杏は誰よりも優しいのだ。誰かが傷つくくらいならば、という思考を彼女は容易にしてしまう。
それは間違いなく彼女の美点ではあるだろう。けれど、常にそうし続けるならば、いつ彼女は思いを届かせられるのだろうか。彼女の恋敵は自らの意思と魅力あるいは能力によって幸せをつかむことができるかもしれない。だが、それではいつ、杏は幸せをつかむことができるのだろうか。
「だけどさ……打席に立たなければホームランは打てないんだし」
春原はそう言って、優しく笑って見せた。それから視線を彼女からそらし、小さく息を漏らす。
「そうしないと、きっと前には進めないんじゃないか、って思うよ。どんな結果だとしてもね」
願わくば、と彼は思う。
彼女にも後悔をしてほしくなかった。彼が恋する少女の恋がどのような結末を迎えようと――できるならば叶ってほしいと思うけれど。
「……心配してくれてるの?」
「もちろん。僕は杏のことが……好きだから」
わずかに言い淀み、彼は照れ笑いと苦みを混ぜ合わせた表情を向けた。
「でもさ、あんたはあたしと朋也をくっつけようとしてるようにしか思えないんだけど……」
「そのつもり、なんだけどね」
苦笑気味に彼は頷く。訝しさとため息をつきたそうな表情を混ぜ合わせた色を瞳に混ぜ合わせて彼を見やり、杏は、だったら、と言葉を続けた。
「なんでこんな手紙を書いたの?」
好きな相手に告白するのにラブレターという方法は確かに古風ではあったが、だとしてもそこには自らの想いを切々と表現するものであるはずだった。
だが、彼が椋に託した手紙には、彼女への想いは短い一文として確かに存在していても、それ以外の――もっと全文でさえ短いものだったけれど――部分には直接的には一切描かれていなかった。
「諦めてほしくなかったから、かな……いや、きっと」
柔らかい笑顔に似たものを表情にさざ波のように乗せ、彼は続けて言った。
「杏に笑っていてほしいから、だろうね」
そんな彼の返事に、杏はため息を大きく漏らし苦笑を浮かべる。けれどそんな表情の中に照れにも似たものを嗅ぎ取り、春原は安堵の息を漏らした。
少なくとも呆れられたわけではないらしい。そのことが彼の心に春の日差しにも似た温もりを与えてくれる。
杏がたとえ朋也に振られたとしても、彼女が自分になびくなどとは思ってもいなかった。もしかすればそんな未来が待ち受けているのかもしれないが、そんなことを期待して――あるいは妄想して居るわけでは決してない。
「でも、何か腹が立つわ」
「なんでさ」
「あんたなんかに言われたことが、よ」
表面に現れた言葉ほどには侮蔑も怒りも交えずに、杏は小さく笑った。懸命に、ではなく、ごく自然な、彼が好きだと自信を持って言える彼女の笑顔。それを見れたことを、彼は確かに嬉しく思う。
「それにしても、あんたバカよね……陽平」
彼女はそう言って、どこか照れ交じりの表情を彼に向け、瞳の奥に決意の色を混ぜ合わせている。それが正負いずれの方向への決意であるのかを洞察することは彼には不可能ではあったが、それでも全てを投げ出す、と言う雰囲気ではなさそうだった。
「でも、ありがとう。陽平」
彼女は身をひるがえしつつ、礼を口にする。
最後に呼んだ彼の名前がもたらした響きには、彼の心を浮つかせてしまうような雰囲気が混ぜ合わされていた。一瞬だけ、恋人となった二人という幻想を脳裏に描きだしそうになり、彼は自らの頭をやや強くかきつつ、屋上から去っていく彼女を見つめていた。
「バカ、か……まあ、そんなことは分かってるんだけどさ」
彼女の姿が屋上と校内とをつなぐ錆つきつつある扉の向こう側に消えてから、春原は小さくつぶやいた。空を覆う雨雲からは、ふたりの時間が終わったことを確認したように、大粒の雨が降り始めていた。
雨を避けるように、校内へと歩を進め、そこから外の光景を眺めやった。空を覆う黒雲、地上に降り落ちる大粒の雨。それらがまるで彼の心を映しているように思えてならなかった。
どうして杏の心に住む権利を唯ひとり有するのが岡崎朋也なのか、という自問自答を彼が為さなかったわけではない。ただその無意味さを知っているからこそ、八つ当たりのごとき言動を誰にも――ひとり自室にいるときでさえ――見せなかっただけだった。
どれほどあがこうと彼女には届かないのであろう、という諦観にも似たものが彼の心を縛りつけ、韜晦しつつそれでも彼女に想いを伝えたくて、手紙を出したのだから。
もし他の人がこんなことをしていれば、彼は馬鹿馬鹿しいと一笑に付したであろう。好きな女の子が恋路へと向かおうとするその背中を押しているのだから。
それでも、きっとこれは価値があることなのだと、彼は信じたかった。あと半年もすれば――卒業してしまった後、彼は実家のある東北に戻らざるを得ないことを想えば――永遠の別れとなるであろう別離の時を想像すれば、こんなささやかな夢であっても、きっとそれだけの価値があるはずだった。。
「それが例え他人から見た痴人の夢であったとしても、ね」
小さくつぶやき、彼は屋上を後にした。
一話 二話 三話 四話 五話 六話 七話
会場に戻る