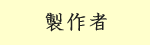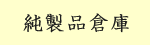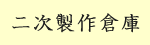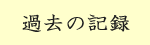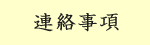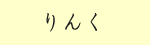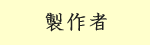
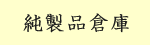
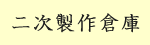
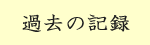
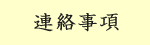
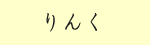
一話 二話 三話 四話 五話 六話 七話
片想い
第四話
椋は双子の姉を見つめながら、何かいいことがあったのだろうか、と思っていた。
最近の彼女は、恒例となりつつあるお弁当づくりの最中でさえ、どこか思い詰めたような表情を垣間見せることが多かったが、明日のお弁当づくりのために下ごしらえをしている杏の横顔には、楽しげなものを見いだすことができた。
双子の姉に何かがあったのだとしたら、と椋は考えようとして、昼休みにおきた出来事を思い出さずにはいられなかった。
春原が双子の姉にと、椋に委ねた手紙。その中身までを椋は知りようもないが、少なくとも双子の姉が怒りをあらわにしなかったことを考えれば、分かりやすい悪口を書いたわけではないのだろう。
そして春原の態度、彼の瞳が時折見せようとする表情は、あるいはラブレターではないのか、という推測が彼女の脳裏に導かれていたが、それでもそれを素直に口に出すには彼の普段の言動が余りにも軽薄であり、それがもたらす先入観とも表現するべきものが椋の口に無形の蓋を形成してしまっていたかのようだった。
ただ、杏が楽しそうであるということ自体は、椋にとっても嬉しいことであった。これまでは聞くことをためらわせるだけの陰鬱さ――あるいはそう悟らせないための作られたような表情が、双子の姉が置かれた状況を尋ねることを憚らせていたことを想うならば、少なくとも悪いことではないはずだった。
「……椋?」
しばらく杏のそばで彼女が行っている弁当の下ごしらえを眺めていた双子の妹に、その杏が訝しげに声を出した。もっとも手は止めず視線も指先に向けられていたから、不快というほどではないのだろうと椋は思い――いつもと様子が異なることを尋ねようとして、椋は一瞬ためらい――数拍の沈黙ののち杏に声をかけた。
「そのお弁当は、岡崎くんのため、なんだよね」
「そうよ?」
「でも、いつもに比べて量が多い気がするんだけど……」
椋の問いかけに、杏は手を止めずに小さな吐息を漏らした。どこか寂しげなそれが、まるで双子の姉の本心であるような気がして、椋はそれ以上問いかけるべきか悩んでしまう。だが、彼女が何かを言おうと口を開く前に、杏が作業を止めて椋を振りかえり、そして小さく笑った。
杏の視線が撫でるように、下ごしらえが終わった、あるいは終わりつつある、想い人に喜んで食べてもらいたいと願う料理になるのであろう、彼女の想いのかけらが込められた、様々な容器に納められたそれらに向けられる。そしてその姿勢のまま呟くように言った。
「もうすぐ……あいつの、朋也の誕生日だからさ。だから、あいつが好きなものを把握しておきたくて……だって最近は、あたしのお弁当の感想言ってくれることも少ないから」
視線を椋に向け、無理をして作ったような笑顔を浮かべた。あるいは杏とそれほど接点のない相手ならば信じたかもしれないが、椋は双子の姉の笑顔が本物だとは到底思えなかった。
「お弁当だけじゃなくてね、プレゼントも探そうと思う。何がいいか分からないけど……でも、朋也に似合う、朋也が喜んでくれるプレゼントを渡したいから」
そう言いきった彼女は、けれども今にも泣き出しそうに見えてしまう。今にも壊れそうな水晶のように、硬質で、けれどもひび割れた雰囲気を感じてしまう。
「……お姉ちゃん」
「でもね」
杏は一度視線を食材へと向け、ややあってから椋へと戻した。悲壮な決意等とは決して呼べない表情を浮かべて、言葉を続けた。
「まだ諦めるわけにはいかないから、さ」
言いきった、というには躊躇いと寂しさを同居させた声質ではあったが、少なくとも椋の反論を封じさせようとするだけの意思を込めた言葉を残し、彼女は再び下ごしらえを始めた。あるいはそうすることで双子の妹との会話をしないで済むとでもいうように、椋を一瞥たりともしようとしない。
あるいは、と椋は思った。
これは、姉にとっての儀式ではないのか、と。想いが届かないことを確認するための、諦めるための。高校二年生のときからずっと思い続けていた長い長い片思いに。
もしそうだとするならば、双子の姉にその決意をさせたのは誰なのだろうか。そう考えて、椋は春原の表情を想い浮かべた。というより、それ以外の誰であっても彼女にこのような行動をさせることができる相手を想い浮かべられなかった。
「……もしかして、春原くんの手紙に書いてあったの?」
そう問われた杏は、一瞬だけ動きを止め、それから嘆息とため息を混ぜ合わせたようなものを口から漏らした。
「陽平は単なるヘタレじゃないかもしれないわね」
そう言って、その彼女の言葉に、じゃあ、と口を挟もうとした、色恋沙汰に興味を抱く少女のような色を瞳と表情の一部に浮かべかけた妹に、それ以上何も言わせないようにするように続けて言った。
「でも、たぶん椋の思ってるようなことにはならないわ、きっと……そうね、今すぐには」
「でも、お姉ちゃんのいい方だと、春原くんのこと嫌ってるようには聞こえないんだけど……」
「嫌いじゃないわよ……でも、あいつは朋也じゃないから……」
それに、と杏は呆れたような声を漏らした。
「例え――本当に例えばだけど。あたしがもし朋也に振られたとしてもさ……すぐに陽平に乗り換える、なんてことができると思う?」
彼女はそう言って、そして小さな息を漏らした。椋には、双子の姉の声質に混ざっている呆れにも似た感情のほとんどが姉自身に向けられているものだと気づき、そんなことはないよ、と言おうとして、結局それを辞めた。
椋にとって恋人である勝平は突然現れた運命の人だったが、第三者の視点から眺めるならば、それまで朋也への想いを口にしていた彼女が突然勝平に乗り換えた、と受け止めることもできるだろう。
けれど、彼女は誰かの同意を得たくて勝平を選んだわけではなかった。朋也への想いが叶わないと知っていたから勝平を選んだわけでもなかった。
ただ純粋に、彼女自身の想いが赴く先が勝平だった、と言うことにすぎない。
それでも、彼女は双子の姉に自らの経験を披露しようとは思わなかった。姉にとって、朋也と言う存在はそれほどに価値のある異性であるはずだから――椋にとっての勝平がそうであるように。
もし自らが勝平に振られたならば、という未来を想像しようとして、けれども椋は結局何も思い浮かばなかった。何かを思い浮かべられるほど――簡単に代替手段を見つけられるような恋では決してないことを、椋ははっきりと知っていた。
それと同じなのだろう。姉にとっての朋也への想いは。
その恋が破れたとしても、すぐに誰かを好きになることなどできるはずがない。
「ごめんね、お姉ちゃん……変なこと言ってしまって」
「いいわよ、気にしないで。それに、そんな言い方をされたら……もう振られるのが決まってるみたいじゃない」
杏はそう言って天を仰ぐかのように視線を上へと向けた。この時間帯ならば夜を飾りつける星星も、自宅の台所と言う場所からでは想像する程度のことしかできない。視界に入るのは見慣れた――所々古ぼけた天井と蛍光灯の明かりだけ。
けれど、杏は、綺麗な夜空を仰ぎみることができなくて良かったのだと思わずにはいられない。
きっと、そんな空の下でひとりたたずんでしまったならば――あるいは椋が一緒でも――きっと泣いてしまいそうになったであろうから。
もし――そう想像することさえ躊躇われてしまうけれど、心のどこかではそれが既定事実だと気づいてしまっている彼女がいた――朋也への想いが届かないと知った時、朋也をめぐる恋の行方を最後まで見届けることができるだろうか、と、そう思った。彼の想いが誰に向けられているのであっても、その想いが叶った時に見せるであろう彼の笑顔を、見たいと願えるのだろうか。
杏に笑っていてほしい、と陽平は言った。彼の想いが届かなくても、杏が笑ってくれていればいい、と。
彼女は――藤林杏はそう願えるのだろうか。春原陽平のように、優しく、哀しく。けれど、そうすることができる彼を、杏は決して疎ましくは思えなかった。
「あたしは、朋也が好きなんだからね」
陽平の顔が脳裏をよぎり、それを無視しようとするように思わずそう口にする。
けれどそれは、恋する少女の純粋な思いではあっても、そこには力強さも意思も感じることができなかった。少なくともすぐそばにいる椋にはそう思えてならなかった。
それでも、例えそれが事実であっても、双子の姉の想いが永遠に届かないとしても、椋は姉を応援したかった。
「ねえ、椋」
姉をそっと見つめ、彼女のために何ができるだろうか、と考えていた椋に、杏が視線を向けながら声をかけた。
「なに、お姉ちゃん」
「好きになってくれた人を好きになることができたら、それって幸せなのかな」
そう言った杏の瞳は、今にも涙がこぼれそうなほどに潤んでいた。それでも目をこすって誤魔化そうとしないのは、それが彼女の強さ――同時に脆さの表れであったのだろう。
あるいは、何も言うべきではないかもしれない。と椋は思う。双子の姉は決して愚昧ではなかった。だから、自らの置かれている状況を、おそらく誰よりも理解しているはずだった。それでもなお、椋にそんなことを尋ねてくるのは、きっと誰かに言ってほしいからなのだろう。
だから、椋は数瞬の沈黙の後に、冗談めいた雰囲気がかけらも含まれない表情で、口を開いた。
「……岡崎くんを忘れるために?」
そう言われた時、杏は確かに想いの中心に突き刺さるものを感じずにはいられなかった。
きつい表現だ、と双子の妹に八つ当たりすることは容易であったが、そうしたところで何かが変わるわけではない。椋が言ったことは極論ではあっても、だからこそ指し示すことができることがあることも事実だった。
春原の想いに応えることは、多分にその意味を含む。好むと好まざるとにかかわらず、そうならざるを得ない。杏の思い出の、おそらく最も大切な部分に朋也はいるのだから。
けれど、杏は頭を振って、そんな思考を頭から追い出した。
目の前にあるお弁当の材料は、朋也のために下ごしらえをしているのだ。心の奥底で哀しくひとり佇まざるを得ない本心のひとかけらが訴える寂しさを春原陽平と言う存在がもしかすれば埋めてくれるかもしれないという期待、あるいは朋也への想いを代替しようとする、そんな杏自身の弱さを、彼女はついに受け入れることが、少なくとも今はできそうにもない。
「……忘れて、椋」
「うん……分かった。でも、お姉ちゃん」
椋は双子の姉に優しい笑みを向けた。一歩近寄り、姉の手をそっと握る。
「未来はひとつじゃないよ。未来は無限にあるんだから」
だから、そんなに思い詰めないで、と妹は姉の瞳を見つめ、柔らかく笑ってみせた。占いが好きな妹らしい表現だと、杏はそう思い、そして少し苦労しながらも妹に比べてまだ固く、けれどそれまで見せていた表情に比べれば柔らかい笑みを浮かべた。
「ありがとう、椋」
「気にしないで、お姉ちゃん。だって、わたしたちは双子の姉妹なんだから」
椋の言葉に、杏はくすっ、と笑うことができた。妹が言ったセリフは、杏がよく口にする表現であったからだった。
いつも、杏が椋を手助けしてきた。有形無形を問わず、ずっと。
けれど、たまにはこういう立場もいいのかもしれない。誰かに支えられ、想われる。それはきっといいことなのだから。
彼女の脳裏に、学校の屋上で礼を口にした相手――春原のことが浮かぶ。
確かに想われること自体が迷惑なこともあるのだろうが、少なくとも彼から向けられた言葉も想いも、彼女の心に深く刻まれていた。
「もし……朋也に手が届かないんだってずっと前に気づいていたら……」
それが無意味な仮定だということに気づきつつ、杏は小さな声で呟いた。
けれど、そこには確かに魅力があった。そのような仮定の世界においては、あるいは陽平からの想いに、より容易に答えを導き出せていたのだろうか。
「……陽平」
そう口の中で呟く。彼の名前がもたらす響きには苦みと甘みの双方を感じることができた。
あるいはそれこそが答えであるのだろうか。
けれど。
「まだ、終わったわけじゃないんだからね」
そう。まだなにも終わっていない。けれど、終わりを知ってしまった時、この苦みと甘みを共に伝えようとするこの感覚を、受け入れることができるのだろうか。その答えを、この時の杏は一切手に入れられそうにもなかった。
一話 二話 三話 四話 五話 六話 七話
会場に戻る